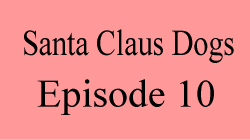
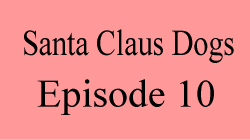
最後に向かったのはポルタ・アルブス(病院)だった。 すでに日付が変わってしまっている。外では花火が鳴り続けていた。もうクリスマスだ。 「あと七つだ」 おれたちは声をふりしぼって、病床の犬をたずねた。 廊下を駆け回っている時だった。 「おい、アンディ!」 ついふりかえってしまった。 背の高い金髪の犬がいた。 (あ) いやなやつだ。いつもおれをいじめているフィンランドの犬だった。 「何やってんだ。その格好」 「あ――その、臨時で」 「サンタのマネか? 歓声が恋しくて、着ぐるみに転身か」 こいつはからむと長い。おれは行こうとしたが、オーバーをつかまれた。 「待てよ」 やつは紙袋を出した。 「ついでだ。くそサンタ野郎。こいつを、あそこの奥の部屋にいる死にぞこないに届けて来い」 おれは袋を見て、彼を見た。どうみてもクリスマス・プレゼントだ。 「自分で渡しゃあいいんじゃないの?」 「おれは忙しいんだ。パーティーに行くんだよ」 「すぐそこじゃない」 「いいから行ってこい」 紙袋を押しつけられる。しぶしぶ受け取りかけた時、劉小雲がおれの前に出た。 「業務に割り込ませたいのなら、事情を話してほしいな。ぼくたち担当が決まっているんだ」 フィンランド野郎はうんざりと、 「ただそこまで行ってくりゃいいんだよ。じじいはスパゲッティ状態だ。ぽいって投げてくりゃいい」 劉小雲はじっと彼を見た。 フィンランド野郎の薄青い目がいまいましげに泳ぐ。 「めんどくせえ。もういい。ほかに頼む」 「サンタ協会の仲間と相談するので少々お待ちを」 彼はおれを引っ張り、仲間のところへ行った。ダニーとクォンと短い相談をして、彼のところに戻った。 「プレゼントを渡してやるよ」 犬がほっと笑った途端、うしろから白い袋が覆いかぶさった。 「!」 おれたちはわっと犬を袋のなかに包み込み、全員でかつぎあげた。 「おい! 出せ。おい!」 「ホッホッホ、ホーッホッホ。メリークリスマース!」 奥の病室に入る。酸素チューブにつながれた初老の男が、目を丸くした。 「クリスマス、おめでとう!」 「そして、かわいいプレゼント!」 もがく袋を置いて、おれたちは笑いながら出て行った。 |
||
 ←第9話へ エピローグ⇒ Copyright(C) FUMI SUZUKA All Rights Reserved |